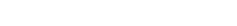甘川にこんなに大勢の人が訪れるとは知らなかった。南浦洞と沙下区の間、谷間の集落・甘川村は車の往来が激しい住宅街だった。聞いたことはあるけれど、いざ行こうと思っても甘川がどこにあるのか知らない釜山の人もたまにいる。生まれてから30年間甘川で暮らし、他の土地に引っ越した友人の一人は、甘川に文化村ができたという話に首を傾げた。「えっ?なぜ? いや、どこに?甘川に?」と文化村ができたことに驚く出身者を見て、いかに長い間町の魅力が隠れていたのかわかるもの。
木村拓哉が映画<HERO>の撮影で甘川村の山腹道路を歩いた頃から、その兆しが表れ始めたのかもしれない。<HERO>に出てきた風景は、空まで届きそうな狭い階段、山の斜面にびっしりと階段状に立ち並ぶ素朴な家々だった。'釜山のサントリーニ'と呼ばれる理由もここにある。どの家も遮るものもなく海が眺められ、急な坂道に張り付くように建つ家々は美しい色で塗られているからだ。家の外観にあまり使わない色も、甘川では見事に調和している。薄いピンク色、濃いピンク色、レモン色、真っ黄色、マゼンタ、ブルー、暗い青緑…。カメラレンズの中で花束のように見える家々は、今の甘川をつくった主役たちだ。たぶん甘川の塗装業者たちは芸術的な感覚の持ち主だろう。
「社長さん、今度うちを新しく塗り替えたいんだけれど」「そうだね、今度はレモン色にしましょう」「隣の家みたいにちょっと薄い赤で塗るのはどうかしら?」「奥さん、色をよくわかっているね。ライトピンクはどうですか?」もちろん、これはすべて想像上の会話。


1号線土城駅で降りて臨時首都記念館に行く。地下鉄構内に備え付けの駅近郊の案内図がある。朝鮮戦争のとき、釜山が臨時首都だった頃は大統領官邸だった。もとは日本統治時代に建てられた慶尚南道知事の官舎だったせいか、西洋式と日本式、韓国式の長所をうまく取り入れている。以前は'景武台'と呼ばれた。李承晩大統領はここで暮らしながら執務を行い、国賓を迎えた。家屋自体が近代建築物としての価値があり、廊下の角を曲がるたびに意外な物を少しずつ発見できる。きれいに敷かれた板の間の部屋に重厚なペチカがあったり、日本式に狭い廊下と階段で他の部屋に行くことができる構造だったり。手で絵付けをして焼いたような陶磁器の小便器もある。裏手には当時の品や文書を陳列した展示館もある。


記念館からは、峨嵋洞を過ぎて甘川の山頂まで歩いて行くこともできるが、デートコースとしてはちょっと大変な道のりなので、マウルバス(小型バス)に乗った方がいい。文化村のバス停はどこかと聞けば、誰もが山頂を指差すだろう。文化村入口の甘川公営駐車場の壁には、村の大きな略図が設置されている。それを見なくても道を探すのは簡単だが、文化村と碑石村の位置を簡単に頭に入れておくと、自分がどこにいるのかだいたいの見当をつけることができる。セマウル金庫のATMの前が村の入口。左右をキョロキョロ見回しながら歩き始める。曲がり角一つを通りすぎるたびに別世界が広がる。壁に繊細に描かれたいくつもの壁画は、余白の使い方とはどういうものなのか教えてくれる。この町に来れば誰もが子供のようになる。住宅を改造したいろいろな店や展示室があり、広めの路地の両側にかけられた看板もシンプルな美しいデザインで統一されている。付き合って10年になる恋人たち、結婚して40年になる夫婦、甘川文化村に甘いムードが漂う。



コミュニティセンターの'甘内オウルト'は、銭湯を現代美術の空間に使っている。建物入口には「毎週月曜日は休みます」という手書きの札と、頬杖をついてまどろむ銭湯のおばさんのオブジェがある。銭湯の大きな浴槽はそのまま使われ、おじいさんが下半身にタオルだけをかけて風呂を楽しむオブジェがある。 屋上の'ハルヌマル'からは町の全景を見晴らせる。



長い間空き家だったのを改築してつくられた展示空間とブックカフェ。元の形を大きく変えず、人の暮らしと芸術はそれほどかけ離れたものではないことを表現している。
夢見る魚、グッドモーニング、人そして鳥、闇の家:星座などのインスタレーションが、色とりどりの童話のような町に溶け込んでいる。その中で一番人気は、セメントの欄干に腰掛けて海と空を見つめる<星の王子と砂漠のキツネ>(ナ・インジュ作)。ひとりで地面に絵を描く子供たちのために現れたように、星の王子と砂漠のキツネの姿がほのぼのさせる。
初めて会った飛行士に、羊を描いてくれと言う無邪気さ、とげが鋭いバラにガラスの覆いをかぶせて心を込めて世話をする純真さ、星の王子になついて、麦畑を見ても王子の金色の髪を思い浮かべるキツネ。そんな王子とキツネのオブジェの間には、一人分のスペースが空いている。だからここに来た人は、並んで待っても王子とキツネの間に座って写真を撮る。子供の頃、うす暗いスタンドの明りの下で寝転んで読んだ<星の王子さま>。その王子が、隣に座った人に「ここに来てよかっただろう」と語りかけているよう。